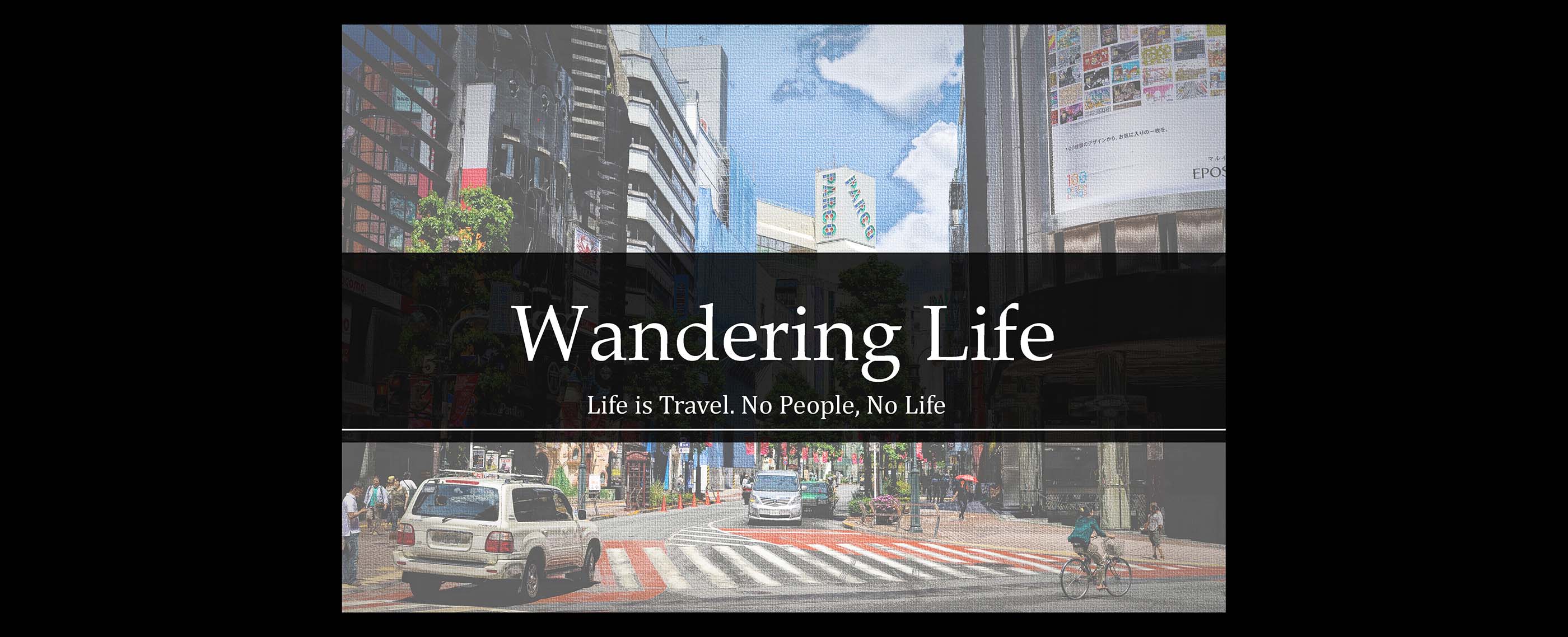最終話 霧海の果てに
美恵と別れてから一旦自宅に帰ると、深夜に車を飛ばして、
理沙のマンションの前へ向かった。
彼女のマンションに着く。
彼女の部屋、401号室はカーテンさえついていないことに気がついた。
心のなかに、大きな暗い影ができていることを感じた。
さっき見た月の光の届かない大きな影。
そこは細長いやさしい女の暗い影。
最初で最後の理沙の怒る声。
それは初めて聞いた理沙の心からの叫び声だった。
本当はもっとたくさん叫びたかったのかもしれない。
きっとそうだ。
なぜ、もっとたくさんの心からの叫び声を聞いてあげられなかったのだろう。
そう思うと居ても立ってもいられなかった。
どうしようもない気分で、マンションの近くにある橋の方まで
走っって行った。
理沙を家に送った時、別れがたくこの橋のそばで二人で川の向こう岸の
夜景を見ながら長時間話し込んだことを思い出す。
理沙の叫び声をもう一度思い返した。
瞳には世界で一番悲しい光が反射していたように思えた。
たとえ霧で目が見えなくとも、理沙の声はもっと聞けたはずだ。
久しぶりに全力で走った疲労感。
鼓動が高まる胸に、透明な空気がすっと入ってきた。
倒れそうな足のはり、強い鼓動。
どれも自分が生きている証であり、誰かに発したい自分の息吹。
確かに今、自分の中にある。
これが久しく感じていなかった生身の自分。
もう今日の仕事などどうでもいい。
橋を歩いてみた。
時折立ち止まっては、理沙とのいろいろな記憶を思い返し、
まだ寒空の下で時間の経つのを忘れ、理沙のことを思い続けた。
橋を往復し終え、川の土手に座り込み、さらに時間が過ぎていく。
空は白々と高層ビルの谷間からかすかに朝の訪れが感じる。
そして今むしょうに人恋しい感覚が襲った。
やっと全ての複雑なパズルの答えが見つかった気がした。
この横に、自分のすぐ横に誰もいない現実。
ガスマスクを取ってまじまじと見る街の光景。
今まで押しつぶされるような見えない重さは、
今確かに払いのけられている。
「理沙」
声を震わせ、体からひねり出すように叫んだ。
周りを見ると、見慣れたはずの通りをはさんだビル群は、
世紀末の地獄絵のように、色を失って見えた。
もう永遠に明るい魂など、この土地からは生まれないかのように。
「理沙」
誰もいない、生命の熱など感じられないこの地で、今自分は
体に熱い確かな生気とエネルギーがみなぎっている。
それは遅すぎる目覚めであり、同時に大切な人を失った痛みの大きさを
ようやく自分が受け入れ始めている感覚である。
「今、横に誰もいない」
一吹きの北風が、通りを抜けて自分の背中を突き抜けていった。
まだ冬の寒さの残る昼下がりの湘南の、海岸から少し石畳で囲まれ
奥ばった砂浜に置かれたベンチに座っている。
あれから一年。
美恵は彼と結婚する、と連絡があった。
私も失業中だし、仕事探さないと生活できないわ、と言い残して。
この美恵のたくましさが自分のような男には頼もしささえ感じる。
理沙の消息はわからない。
自分は成長したのかどうかもわからない変化のない生活を
相変わらず続けている。
今は自分に何が足りないのか?がわかっている。
しかし、その足りないものを今の自分は充足しているのか?
この問いかけは、この一年で最も辛い作業であり、
またこの作業がせめてもの自分の悔いと理沙に対する懺悔の作業でもあったのだ。
後悔と自分への責めは、一年前よりも今の方が大きい。
そう。日毎の自分の限界に対する歯がゆさが現実の感情となって、
内面に噴出すように大きくなっているのだ。
もう理沙のような女性に出会うことはないだろう。
これからの残りの人生で、まだどのような人と出会い、
心震わせるような感動をするのか?
あるいは締め付けられるような後悔をさらに続けていくのか?
しかし、たとえ自分が自分の能力の限りにおいて、
精一杯の生き方を過ごし、どのような喜怒哀楽に富んだ人生を送ったとしても、
理沙のような女性が自分の横にいて、成熟した大人の男女として、
心から豊かな空間と時間を過ごしているようなイメージを抱くことができない。
それだけは確信的に思えるのだ。
仕事が終わり、いつものカフェ・バー「No Direction Home」に立ち寄って、
今や数だけは増えた常連のなじみ客と、オーティス・レディングのライブアルバムの裏話を話そうとも、
休日に、知り合いの別荘のプライベート・ホテル的な部屋で、
ワインを片手に本をゆっくり読むふけっても、孤独は自分の心の中で、
中国大陸上で発達する大型の低気圧の厚くて暗い雲のように
広がっては覆い尽くしていく。
二人の間の魂だね、と昔に行ったことを思い出した。
二人の縁を切ったということは、二人の魂を殺したのと同じなのだ。
そう、それはどういう意味なのだろう?
今ようやくわかった。
二人の間で作られた愛情という魂は、二人の命の相応分が分離して作られたものなのだ。
“かつて、僕たちは愛し合って、二人の間に魂を作った”

たとえ期間限定だったとはいえ、確実に自分達は愛し合い、
二人の間に情念が強く結びつき、独立した魂が宿っていたのだ。
その魂が、“忙しい””苦しい“という流れの中で、
自らその魂を断ち切ってしまったのだ。
今、自分が半分生きているのか死んでいるのかわからない状態の説明がこれでつく。
自分なりに命を託して愛した恋愛を断つということは、
自分の命の半分を絶ったということなのだ。
頭の中に、白い砂丘の上に無音で光る雷のような強烈な白い光を感じた。
自分の意識の中で、何か止められないオーケストラの指揮者の合図のように何かが始まったのを感じた。
胸が急に締め付けられるような痛みがした。
もう半分の炎の魂は、自分の残りの重い十字架を背負ったような人生を全うすることができないことを感じた。
息が苦しい。
今までの息の苦しさとは一段違う痛みを感じた。
通りの反対側の通行人は私の異常さには恐らく気づいていないだろう。
静かな訪れ。
ガスマスクの中で、静かに目を閉じた。
自分の人生はいつからこんなに重くなったのだろう。
自宅の中に覆い続ける白い霧は、いつから発生したのだろうか。
家の中で時折聞こえる子供の声。
白い霧が少しずつ消えていく。
長らく暗い室内だった空間からそこにいる人の顔がぼんやりと浮かんでくる。
記憶が遠ざかっていく。
右手がしびれ始めている。
もうこれ以上、待っていられない。
朦朧とする頭の中で、少し熟考して、意を決した。
もうたくさんの行動はできない。
将棋で言えば最後の一こまをどこに置くか?ぐらいの余力しか残されていなかった。
迷うことはない。
両手で精一杯の力で、頭の後ろに締め付けたマスクのベルトをはずし、ガスマスクを脱いだ。
苦しい時に肌身離さずつけていたガスマスク。
それを一番息苦しい今、とりはずしたのだ。
後悔も、絶え絶えとした呼吸も、今は遠い出来事のように感じ始めていた。
観念した自分の意識に、鼻からすーと空気が入って肺を通っていった。
もう目を開ける力もなく、机に頭を突っ伏していた。
思いもほか、空気は新鮮に感じた。
「そう、この感覚。
この感覚で、もう一度最初からやり直せたら?」
“最初”
最初っていつからだろう?
何をやり直すのか?
自分の人生?
理沙との時間?
全ての問いかけも遠い意識の中で、あいまいな言葉となって溶けていった。
弾力を失い硬く閉じた目から一筋の涙が力なく頬を伝わり、
椅子の下の砂場に落ちていった。
春の暖かい砂は熱を持ち、たった一滴の水滴は、
あっという間に蒸発していった。
もし目を開けることがあれば、どこの世界を見ることになるのだろう。
そこで出会った新しい大切な人に、今度こそやさしくなれるだろうか?
大切な人の声に心から耳を傾け、その人と共に生きる。
その人が幸せな笑みを浮かべるのを確かに見届けたら、
もう再び目を開く必要もあるまい。


(終)