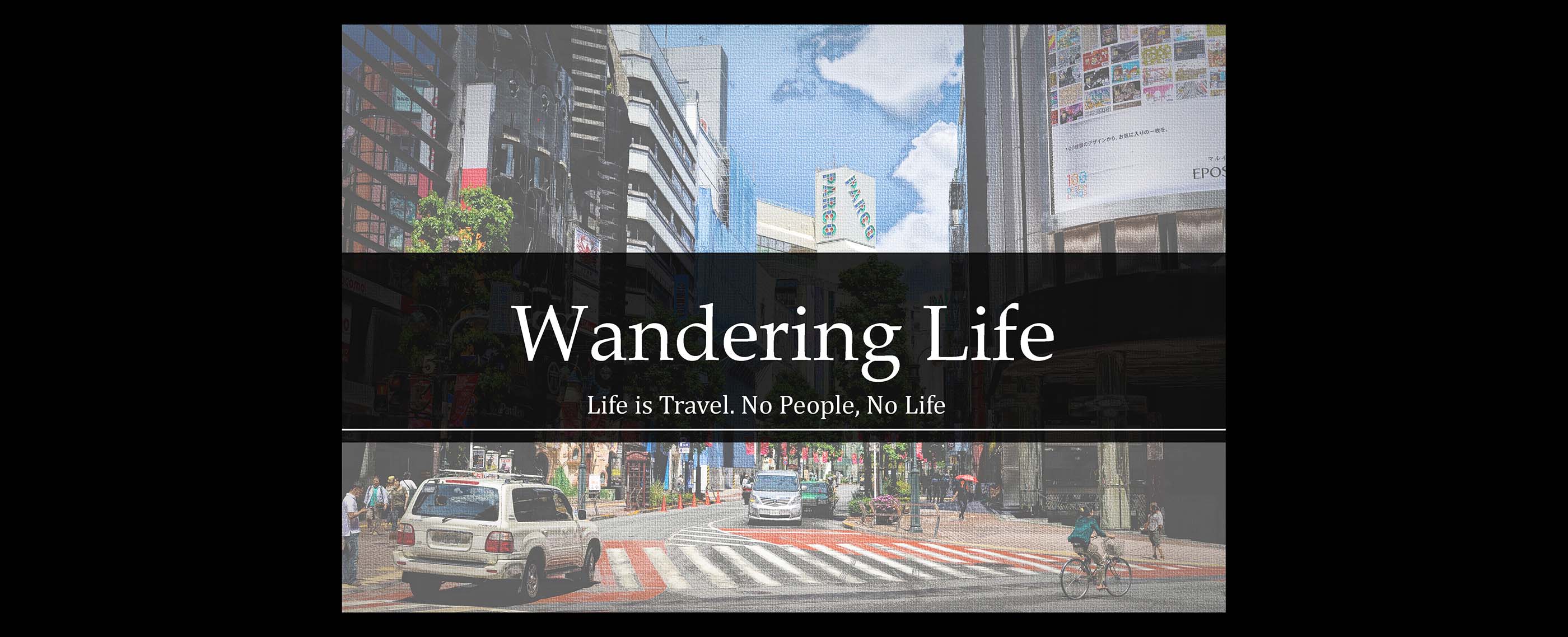第二話 至極のひと時
柔らかいベッドに身を落とすと、安らぎは体の中から天井を抜けて、
さっき見てきた夜空の果てまで昇華していく感覚になる。
そう思わせるのは、上質なホテルのベッドのシーツのせいだけではない。
隣には栗色の髪を枕になびかせ、こちらを見ている理沙の瞳の魔力のせいだ。

理沙と出会ったのは2年前。
白い霧が家や職場を覆い始め、ただ日々を暮らすことさえが重く感じられた頃、
仕事の印刷デザインの関係で東京ビッグサイトのイベントの出展した時の事だ。
業界の実情をよく知りながらも、デザインのビジネスに対する訴求力を真面目に追求している姿が強く印象に残った。
デザインの趣向や仕事に対するスタンスにお互い惹かれあい、話す内容に事欠かなかった。
思えば30代後半になるこの年までわき目も振らず実直に仕事を続け、
自分の事務所を持ち3年が経った。独立当初の高揚も不安も落ち着いたものの、
社員を抱えて仕事を継続し続けなければいけないという、
現実の不確かで大きな不安を知ることとなり日が経つ。
現在が自分の人生にとって新しい節目なのだろう。
理沙との時間は今までの自分に決してなかった充実した時間だ。
夫婦でも恋人でない、パートナーという言葉がぴったりくる。
もちろん愛し合っていると心から思えている。
二人で愛し合い、体がつながる度に二人の間に情が育まれてきたのがわかる。
ベッドで寝そべりながら、
「二人のへそとへその間に、白い魂の生物がいるみたい。」
と理沙は言う。
子供だけが愛の結晶ではない。
二人が深く愛し合った時点で、目に見えない二人の絆が一つの独立した魂として
生を受け存在するのだ、と思うようになる。
華やかなような世界で、仕事一筋で堅物的にやってきた自分にとって、
どう相手に接して、相手に何を与えて相手に何を求めたらよいか?
戸惑いと不安に感じることがあるが、それも幸せの中の贅沢な不安と言い聞かせた。
これだけ愛している人間がいるのに、日常に戻ると、
別の人間が浮遊しているように不確かな気持ちになる自分がいつももどかしい。

ホテルに備え付けのラジオをボリュームを控えめにしてつけてみる。
勢いのあるピアノの音がまるでこの部屋の二人に向かって跳ねるように響き渡った。
「この音楽はなんだろう?」
「アシュケナージよ。懐かしいわね。」
幼少からピアノを習っていた理沙にとっては、日常を思い起こさせる曲だったかしれない。
ベニー・グッドマンでもかかれば、何か止め処もない空想話でもできたかもしれない等と思ったが、
口には出さなかった。
ラジオを消した。
音楽など必要ないのだ。
柔らかい肌の感触と甘酸っぱい香り。
理沙と出会ってからは、しばしの時間とはいえ、
自分にとっては極上の時間を味わえる。
いつから始まったのか、そしてこの先どうなるのか?
今考えなくてもよいことを自分は考えてしまう。
理沙の細い腕が体に絡み付いてくる。
目をつぶり、もう一度ゆっくりと匂いを味わってみる。
昼間中、息苦しさで締め付けられた肺が、
すーと穏やかに緊張を解かれていくのがわかった。
(第三話へ続く)