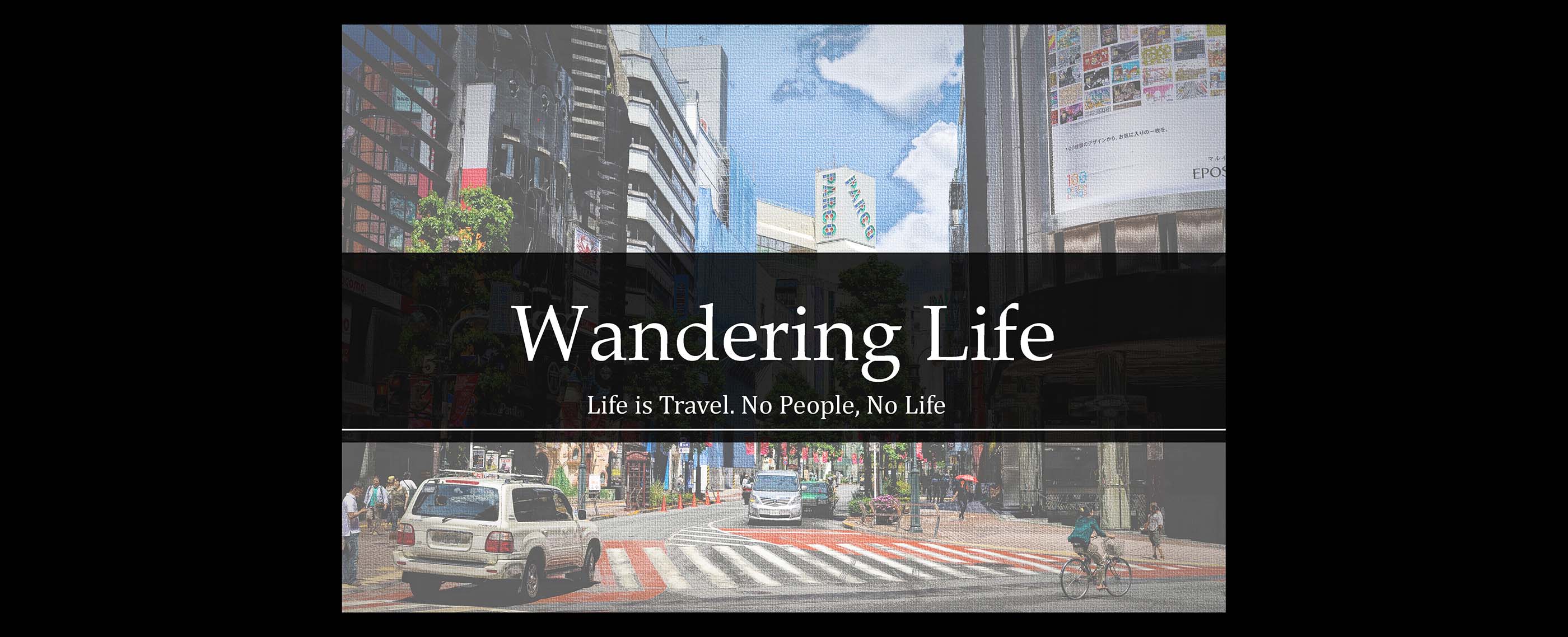第九話 横に誰もいない

美恵と別れてから一旦自宅に帰ると、深夜に車を飛ばして、
理沙のマンションの前へ向かった。
彼女のマンションに着く。
彼女の部屋、401号室はカーテンさえついていないことに気がついた。
心のなかに、大きな暗い影ができていることを感じた。
さっき見た月の光の届かない大きな影。
そこは細長いやさしい女の暗い影。
最初で最後の理沙の怒る声。
それは初めて聞いた理沙の心からの叫び声だった。
本当はもっとたくさん叫びたかったのかもしれない。
きっとそうだ。
なぜ、もっとたくさんの心からの叫び声を聞いてあげられなかったのだろう。
そう思うと居ても立ってもいられなかった。
どうしようもない気分で、マンションの近くにある橋の方まで
走っって行った。
理沙を家に送った時、別れがたくこの橋のそばで二人で川の向こう岸の
夜景を見ながら長時間話し込んだことを思い出す。
理沙の叫び声をもう一度思い返した。
瞳には世界で一番悲しい光が反射していたように思えた。
たとえ霧で目が見えなくとも、理沙の声はもっと聞けたはずだ。
久しぶりに全力で走った疲労感。
鼓動が高まる胸に、透明な空気がすっと入ってきた。
倒れそうな足のはり、強い鼓動。
どれも自分が生きている証であり、誰かに発したい自分の息吹。
確かに今、自分の中にある。
これが久しく感じていなかった生身の自分。
もう今日の仕事などどうでもいい。
橋を歩いてみた。
時折立ち止まっては、理沙とのいろいろな記憶を思い返し、
まだ寒空の下で時間の経つのを忘れ、理沙のことを思い続けた。
橋を往復し終え、川の土手に座り込み、さらに時間が過ぎていく。
空は白々と高層ビルの谷間からかすかに朝の訪れが感じる。
そして今むしょうに人恋しい感覚が襲った。
やっと全ての複雑なパズルの答えが見つかった気がした。
この横に、自分のすぐ横に誰もいない現実。
ガスマスクを取ってまじまじと見る街の光景。
今まで押しつぶされるような見えない重さは、
今確かに払いのけられている。
「理沙」
声を震わせ、体からひねり出すように叫んだ。
周りを見ると、見慣れたはずの通りをはさんだビル群は、
世紀末の地獄絵のように、色を失って見えた。
もう永遠に明るい魂など、この土地からは生まれないかのように。
「理沙」
誰もいない、生命の熱など感じられないこの地で、今自分は
体に熱い確かな生気とエネルギーがみなぎっている。
それは遅すぎる目覚めであり、同時に大切な人を失った痛みの大きさを
ようやく自分が受け入れ始めている感覚である。
「今、横に誰もいない」
一吹きの北風が、通りを抜けて自分の背中を突き抜けていった。

(最終話へ続く)